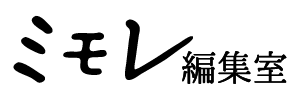息子が小学校に入学してから11ヶ月。早いもので4月には2年生になります。
入学当初は持ち物の多さ、決まり事の数々、時間割にそって動く集団生活になかなか慣れず「保育園に戻りたい。学校に行きたくない」と泣く日もありました。ゴールデンウィーク前後がそのピークで、これが小1の壁のひとつか...と悶々とするときも多々ありましたが、夏休み明け頃から段々と自分のペースや居場所を見つけ、最近は顔つきも随分逞しくなったと思うこの頃です。
それでも時々日曜日の夜に「あしたから学校嫌だな〜」とボソッと呟いたり、週中頃に「あと何回寝たらおやすみかな?」と聞かれると、あれ?大丈夫かな?とドキッとしたり。登下校時や学習参観ではお友達と楽しそうに過ごしていますが、学校という場に対して何らか葛藤があるのは感じています。不覚にもその葛藤に対して何と声をかけるのが正解なのかわからず、"そういうもの"として存在するモノコトが世の中にはあるよという思いで「学校を楽しもうとがんばらなくてもいいよ」とだけ伝えています。
息子の社会を知る
先日、映画「小学校〜それは小さな社会〜」を観てきました。毎週日曜日の朝にJWAVEで聴いているラジオ番組アクロスザスカイのゲストに監督の山崎エマさんが出演されていたのがきっかけで公開を知りました。山崎さんはイギリス人のお父さんを持ち、小学校時代を日本で過ごしています。その後中・高はインターナショナルスクールへ進み、アメリカの大学へ進学。年齢を重ねて、責任感や真面目さなど周囲から自分に対する評価のルーツが小学校時代にあると気づき、日本の小学校の姿を世界に発信したいと長年企画を温めていたそう。
今の小学校がどんなところなのか、息子が1年生を終える前に観ておきたいと思い@ともみ さんも鑑賞されていて、これは観ない理由がない!ということで行ってきました。
♦︎♦︎♦︎
ここからはかなりネタバレで書きますので、これから観る予定の方は飛ばしてください。(後で感想をシェアできたら嬉しいです😆)
映画は1年生と6年生に焦点を絞って、学習だけでなく掃除や給食の配膳、様々な係りの分担など学校という社会の中に自分の役割がある生徒と、それを全力で支える先生たちの日々に丁寧に密着しています。日本の教育で育った私は学校生活はそれが当たり前だと思っていましたが、山崎さんはあるインタビューで日本の小学校教育は世界から見るとかなり特殊で、この6年間に日本人らしさといわれる協調性や勤勉さの基礎が培われるとお話されています。
映画冒頭は入学準備をする親子のやり取りから始まり、入学式、ランドセルや帽子のしまい方、上履きの揃え方などを教わる様子など慣れない学校生活を始める1年生の様子が次々と流れます。小さな体と危うげな手つき、真っ直ぐで一生懸命な子どもの眼差しが息子に重なって出だしから涙腺が崩壊。ポロ泣き、ボロボロ泣き、涙の量は変われど、とにかく涙と鼻水が止まりません。
入学当初は、いつもニコニコ穏やかだった息子の表情が不安げになり、毎日のルーチンが進まない、ちょっとしたことで泣く、何を聞いても話したくないと俯く、そんな息子の変化に不安になったり時に怒ってしまったこともありましたが、あのとき彼は初めて学校という社会のルールに直面し、小さな体と心で必死に耐えていたんだな(そして今も)と思うと、とにかく泣けて泣けて仕方なかったです。そばにいたのに私は息子の何を見ていたんだろう。愚かな自分の情けなさで胸がいっぱいでした。
6年生が1年生を見て「わたしたちってあんなに小さかったっけ?」と話す場面では、その大人びた表情にドキッとします。男女の精神年齢の違いが如実に表れるシーンもたくさんあって面白かったです。そういえば私も小学生のとき、男子の言っていることがよくわからないと思っていたな~(笑)
先生も人間
恐らくは私と同世代くらいの先生たちの葛藤や奮闘する姿にグッとくる場面も多くありました。現在は教師の労働環境の過酷さばかりが報道されていますが、映画全体を通して感じたのは先生自身も日々成長して感動していること。早朝から深夜まで働き、やることの多さやイベント開催時の負担、撮影期間はコロナ渦だったのでオンライン授業の工夫など、そのご苦労は察するに余りあるほどでしたが、それを差し引いても先生の心に残る教師としての誇りを随所に感じました。
1年生にお母さんのように寄り添う優しい先生、6年生に「自分の殻を破れ!」と発破をかける体育会系ど真ん中の先生。自分が過ごした学校にもこんな先生がいたな~と思い出しつつ、あの頃は雲の上のような存在だった先生を社会で働く同志、子どもを預ける親の目線で見つめる感覚が不思議でした。
「毎日が平均台の上に立っているような、ギリギリの感覚で仕事していますね」という先生の言葉が心に残っています。先生も人間、当たり前のことですが、先生には強く優しくあってほしい、そんな生徒と親の期待が時に先生を追い詰めるのかもしれません。
成功体験の素晴らしさ
映画のラストは、1年生が新1年生の入学式に歓迎の歌を披露するための練習風景にフォーカスされます。花形楽器のシンバルをオーディションで勝ち取った女の子。日常では感情が少し不安定な部分もあり、担任の先生をお母さんのように慕う甘えん坊さんです。楽器を勝ち取ったはいいものの、個人練習をさぼり全体演奏では叩く箇所を間違え皆についていけません。「楽譜を忘れたから」と言い訳をする女の子を音楽の先生はこれでもかというくらい強く𠮟ります。お願いだからそんな怒らないであげて・・・もしこれが我が子だったら・・・と思うとやるせなくハラハラドキドキ。でもそんな彼女を担任の先生や周囲のお友達は見捨てず励まし続け、彼女自身も楽器担当を諦めず練習を続け、ついに散々叱られ続けた先生からリハーサルを終えたときに「頑張ったね!」と褒めてもらえるのです。そのときの表情の晴れやかさといったら・・・!!!自らの力で越えた山でしか見えない風景ってありますよね。その体験こそが人を成長させる素晴らしさを目の当たりにしたエピソードでした。
そして彼女は映画の終盤でお友達とこんな会話をするのです。
「わたしたちって何なんだろうね?」
「みんなひとつひとつが繋がって大きなハートになってるよね」
まるで小1の会話とは思えない!少なくとも今うちの息子は自分の存在について考えるような様子はまったくなく、いつかカメカメハができる日が来ると信じて戦闘力を上げるべく修行のような動きに励んでいます(笑)怒られる息子の姿を想像するのは辛いですが、いつか彼もこんな成功体験をしてほしいと切に願います。
知って、考えよう
山崎さんは「日本の小学校教育を賞賛したいだけではなく、現実を撮りたかった」とお話されています。個性を大切にする海外の教育も素晴らしいし、様々な国の文化や教育を知って皆で考える機会を持つきっかけにしたかったと。撮影は2021年のコロナ禍、山崎さん自身は妊娠中というとても大変な撮影期間だったと思いますが、コロナ禍でも学舎を止めなかった大人と子どもの努力を記録として残せたことや、山崎さんが母になる変化を感じたから撮影できたシーンがあったかもしれないなど、特殊な状況が重なってこそ完成した作品のようにも思います。
私は親目線で鑑賞しましたが、既婚、未婚、子どもの有無関係なく、観る人それぞれの心情に刺さる部分があるはずです。
息子がどんな社会にいるのか、こんなに至近距離で教えてくれる作品に今のタイミングで出会えて本当によかったです。これから息子と学校とどう関わっていくかを考えたり、教育現場で起きているニュースにもっと関心を持とう、など心境の変化を自覚しています。短編版がアカデミー賞にノミネートされて、結果発表も楽しみです。
鑑賞後、私が息子にできることは何かと改めて考えましたが、息子がいつでも戻ってこられる安全地帯を作る、これに尽きると心底感じています。お腹と心を満たすご飯を食べて、温かくて清潔なお布団で寝るといった生理的な安全はもちろんですが、求めれられたらいつでも抱きしめてあげられる心理的な安心をあげたい。そんな心の余裕を持っておくためにもやっぱりご自愛は必須だと、自分の信条も再確認!凄まじいスピードですぎる毎日ですが、なんてことない日々の積み重ねの中に親子共々成長があると実感しています。